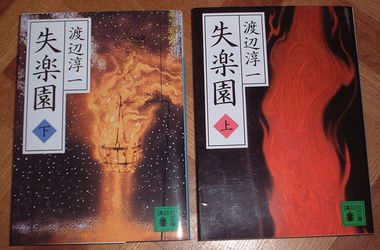
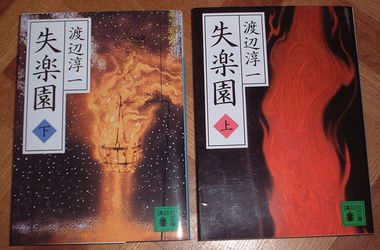
慎始敬終
ごく一部の方からレビューを期待されましたので、ちょっと書いてみます。
日経新聞掲載の【愛の流刑地】の続きが気になって仕様がない今日この頃でありましたが、今日無事連載が終了しました。
(この連載小説のおかげで、日経新聞への考えが(悪い意味で)少し改まったものです。)
にっけいしんぶん日記さんを見て大きく頷きながら読み進めた一年。終了した今は感無量という感じであります。(あんまし良い意味ではなく)
さてさて、愛ルケはおいといて失楽園の話をば。
かつて大ベストセラーとなったお話です。
映画化、ドラマ化された記憶があるのですが、いまいち食指が動きません。
おかげさまで、結末だけは僕も知っておりました。
はてさて、お話の内容はいわゆる不倫モノなわけですが、どうにもこうにも、あらゆる部分で理解しかねる箇所が多かったです。
なんとひとりよがりな、とあきれてしまうこともしばしば。
また、結末だけは知っていただけに、読みながら「え、もうそんな兆候が?」などと思いつつ。
しかし、この結末について、何度考えても唐突過ぎる、と感じました。
あと、判っていたこととはいえ、エロいシーンが多すぎなのもちょっとどうかと。
文庫にて上下巻の内容でしたが、エロを削減して、登場人物の心境変化に重きを置いたならば、もしかしたら良いお話になったのではなかろうか、なんて思ったりします。
(もしかして、これをするとダメだという向きもあるのかもしれませんが)
ところでこのお話、単なる官能小説(違)と思いきや、突然聞き慣れない単語が突然出てきたりしてびっくりします。
僕の学がないのが仕方ないことだろうと思うのですが、「毒を失ったコキュ」なんぞと表現されても、素で判りませんでした。
なんとなく悔しいのでちょっと調べてみたら、フランス語で「妻を寝取られた男」だとか。
「へぇ」とか思いつつ、このページを書き終える頃には忘れていることでしょう。
また、阿部定事件についても妙に詳しく書かれていたりします。この本のおかげで詳しく知ることができました。
ためしにほぼリアルタイムに近い時に体験したであろう、祖父母に聞いてみたところ、久木(渡辺氏)の見解とはいささか異なっていたようです。
まぁ、見方はいろいろなのでしょうか。
そういえば有島武郎のお話がでてきたりしますが、死後の事ばかり言われては彼らも浮かばれまい、などと思いつつ。
渡辺氏の趣味なのか、妙に着物関係の単語が登場してきます。
帯についてだとか、「付け下げ」とか言われてもすぐピンと来る人は少ないかと。
たまたま着物好きなお友達がいることもあってちょびとだけ見識がありましたのでなんとかなりましたが、人によっては襦袢がどーのと言われても困るような・・・。
果たして、ここらも読者層を考えると別段問題ないのでしょうか。
そうそう、「性のエリート」なる珍妙な表現がでてきます。
これは【愛の流刑地】でも継続使用がなされていることもあり、渡辺作品を理解するに極めて重要な言葉のようです。
その後、「愛の暴力団」とか「ヤクザ」だとか素敵すぎる言葉が沢山使われることに。
ちなみにこの本、BOOKOFFにて手に入れてきたわけですが、これは早々に同じ場所に帰してくるべきか、などと思いつつ。
(ネタで本を読むようになっちゃいけませんな)
思えば渡辺さんの本は【幻覚】と、【愛の流刑地】と、【失楽園】しか読んだことがないわけで、まだまだ経験が足りないのかもしれません。
気が向いたら他の本も読んでみることにいたします。
日経新聞をお読みの方、不倫モノがお好きな方、渡辺淳一さんのファンの方に、おすすめです。
#最近このページに書く行数は控えめに、を心がけていたのに、ついつい行数が増えてしまいました。不思議なものです。